東京で年収500万円はきつい?――結論(先に要点)
年収500万円(額面)の個人の**手取り目安は概ね 年間約380〜420万円(=月約31〜35万円)**です。
東京では「家賃」「子育て費用」で状況が大きく変わります。独身なら工夫でやりくり可能、子育て世帯は共働きや固定費見直しが現実解になることが多いです。
この記事で得られること(要約)
- 年収500万円の手取りのざっくり目安が分かる。
- 家賃や食費など、都内での生活イメージが持てる。
- 「まず取り組むべき改善策(優先順)」が分かり、次の一手を打てる。
想定
30〜40代、東京在住または転勤で東京勤務。
年収はおおむね500万円前後で「貯金が増えない」「子どもができたら不安」という方。
読みやすさと実行しやすさを重視します。
早見表 — 世帯構成別の手取りイメージ(概算)
| 世帯構成 | 年間手取りの目安 | 月の手取りイメージ | 一言ポイント |
|---|---|---|---|
| 独身(扶養なし) | 約380〜420万円 | 約31〜35万円 | 家賃を抑えれば貯蓄可能。 |
| 共働き(世帯合算) | 配偶者収入に依存(例:合算で約650〜800万円) | 合算で約54〜66万円 | 世帯では余裕が出やすいが支出も増える。 |
| 専業主婦+夫(夫500万) | 個人手取りは上記 | 約31〜35万円 | 税負担は減るが家族分の支出が増える。 |
| 子ども1人あり | 個人手取りは上記 | 約31〜35万円 | 保育料・教育費で貯蓄は圧迫されやすい。 |
| 子ども2人あり | 個人手取りは上記 | 約31〜35万円 | 都内ではかなりタイト。共働きが現実解。 |
※上は概算レンジです。控除・保険料・自治体ごとの料率などで変動します(詳細は下部「計算前提・出典」参照)。(国税庁)
手取りはどう出すか(ざっくり流れ)
- 年収から「給与所得控除」を引く。(国税庁)
- 厚生年金・健康保険・雇用保険などの社会保険料(本人負担)を差し引く。(年金機構)
- 基礎控除などを差し引いて課税所得を算出し、所得税・住民税を計算する。
- 年収 −(社会保険+所得税+住民税)= 年間手取り(概算)。
(詳細計算は記事末に簡易例を掲載しています。面倒な方は「目安」を信頼して読み進めてください。)
都内での家賃相場(感覚値) — 生活への影響が大きい
- ワンルーム/1K:約6〜11万円(駅・区により差あり)。(SUUMO)
- 1LDK〜2LDK:12〜18万円(場所によっては20万円超)。(SUUMO)
- ファミリー向け(2LDK以上):15万円〜20万円以上が一般的。
家賃が月10万円台前半と15万円台では、貯蓄余地が大きく変わります。家賃は手取りの25〜30%以内に抑えるのが安定への近道です。
生活費の実例(単身・簡易シミュレーション)
- 家賃:10万円
- 食費:4万円
- 光熱・通信:2.5万円
- 交通:1万円(会社負担がない場合)
- 交際・娯楽:4万円
- その他(保険・雑費):2.5万円
→ 合計:約24万円/月。月手取りが31〜35万円なら貯蓄は可能だが余裕は大きくない。家賃が15万円だと貯蓄余地はほぼ無くなります。(SUUMO)
子育て世帯の場合(ざっくり)
- 保育料/幼稚園費:自治体や認可・無認可で差あり(公的補助の有無で負担が変わる)。
- 習い事や塾を含めると**+2〜6万円/月**は現実的。
- 結果:年収500万で片働きのみだと貯蓄がほぼゼロ〜赤字になりやすい。共働きが現実解になる家庭が多いです。(総務省統計局)
優先度の高い改善策(効果順で実践しやすいもの)
- 家賃の見直し(最優先)
- 手取りの25〜30%目安。都内でもエリアや通勤時間で大きく変わるので妥協ポイントを決める。(SUUMO)
- 固定費の削減(通信・保険・サブスク)
- 格安SIMや不要サブスクの整理で月数千〜数万円の節約に。(厚生労働省)
- 制度の活用(ふるさと納税・NISA・iDeCo)
- 税の効率化と長期資産形成で将来の安心を増やす。(国税庁)
- 収入の複線化(副業/スキルアップ)
- 即効性は低いが、中長期で年収を押し上げる現実的手段。
- 家計の「見える化」
- 家計アプリで3ヶ月記録し、削るべき出費を洗い出す。
実用チェックリスト(まず30日でやること)
- 今月:家賃が手取りの30%以内かチェック。NGなら候補エリアをリストアップ。
- 今月:通信費とサブスクを見直し、1つ減らす。
- 3ヶ月:毎月1万円を自動積立(習慣化で精神的負担も軽くなる)。
- 6ヶ月:収入アップのために習得すべきスキルを1つ決める。
併せて読んでみる
まとめ
年収500万円は決して低くありませんが、「東京での暮らし」は家族構成や家賃で大きく変わるのが現実です。
まずは家賃と固定費を見直し、少額でも確実に貯める習慣を作ること——これが最短で心の余裕を取り戻す道になります。
焦らず小さく改善を始めましょう。
計算の前提・出典
簡易計算の前提(この記事で使った概算)
- 給与所得控除は国税庁のルールに従う。(国税庁)
- 厚生年金の保険料率は18.3%(事業主と折半)。被保険者負担はその半分の目安で計算。(年金機構)
- 健康保険(協会けんぽ・東京都)は令和7年度の料率を参照(東京都 9.91%)。(協会けんぽ)
- 雇用保険の労働者負担は令和7年度の案内を参照(5.5/1,000=約0.55%)。(厚生労働省)
- 家賃相場はSUUMO等の不動産相場記事を参照(ワンルーム〜ファミリー帯のレンジ)。(SUUMO)
主な出典(要点)
国税庁(給与所得控除のルール)・年金機構(厚生年金料率)・全国健康保険協会(協会けんぽ料率)・厚生労働省(雇用保険)・SUUMO(家賃相場)など。(国税庁)
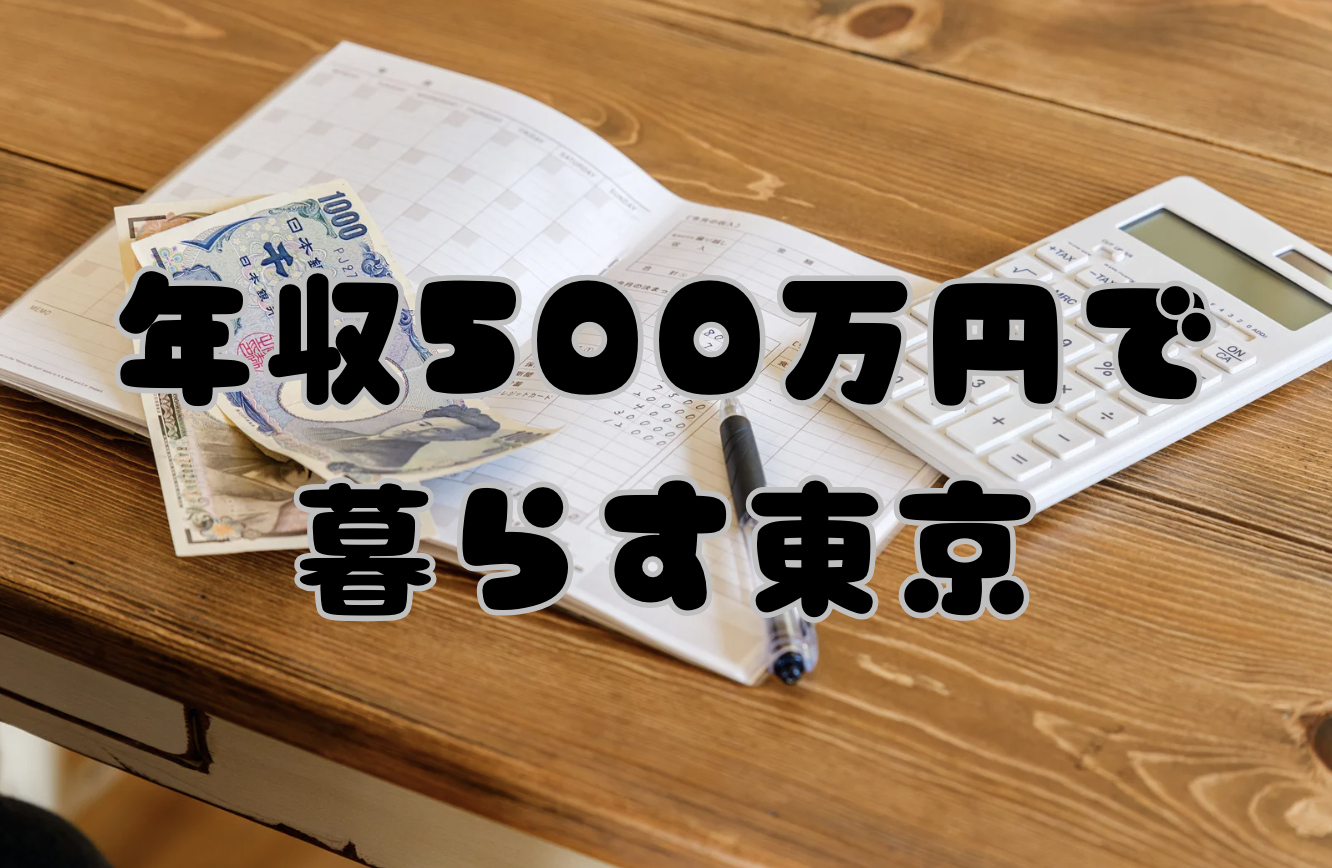
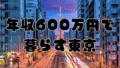

コメント